3.寒冷前線性降水域(その1)
|
ブラウニングとハロルド(既出)は、英国で観測された幅の狭い寒冷前線性降水域をドップラーレーダのデータを用いて、初めて詳しく解析した。その後、米国の西海岸、東太平洋、アラスカ湾等の事例で多くの研究が行われた。前線付近の運動学的・熱力学的構造、降水の生成と分布等に着目してこれらの結果を検討し、日本付近の線状降水域の解析の参考にしたい。
始めににブラウニングとハロルド(既出)の事例を調べる。
図11は、1969年2月6日12UTCの天気図で、実線は地上等圧線(4hPa毎)、破線は1000hPaと700hPaの層厚(10m毎)である。Pはレーダー観測地点を示す。地上寒冷前線(以後単に前線)が通過するとき、強い雨や雹が降り、場所により雷鳴も観測された。前線は、前線に直角方向におよそ12m/sの速さで移動した。前線後面の雲域の境界はハッチで示され、点彩は降水域(斜線は強い降水域)である。前線の位置に巾の狭い強い降水域があり、可視画像(省略)でも対応して幅の狭い長い雲域がある。前線から後方の雲域の境界までの距離はおよそ170kmある。この事例では前線前縁の巾の狭い寒冷前線性降水域からおよそ75km後方まで雨域が続いている。以後、前線に沿う方向には一様と仮定し、前線に直交する断面図で議論する。 |
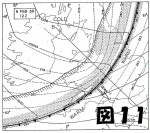 |
図12は、前線を挟む巾4km程度の鉛直断面内での循環を示す。縦軸は地上からの高度(km)、横軸は前線の位置(0)からの距離(km)である。2月6日1124UTC~1125UTCの結果で、図の実線は前線に相対的な流線、破線は鉛直流(m/s)である。高度3km付近のハッチ域は降水エコーの上端を示す。鉛直流は前線に直交する風の成分から、連続の式を積分して計算されている。上昇流2m/s以上の区域は巾が2km以下で高さ2.2km程度の狭い範囲にあり、最大値は高度1.2kmにあっておよそ8m/sである。これが線状対流の上昇域である。図から推定されるように、大気境界層内に大きな水平収束がある。水平500m、高度500mの範囲では10-2s-1にも達していた。高度1km以下の寒気側には直交成分は殆ど存在していないから、前線の前方500mの距離で暖気側の直交成分が5m/s-1減少することに相当する。
図12の右側に、前線の前方2kmでの前線に相対的な直交成分の鉛直分布が示されている。直交成分の最大値は前線の移動速度、12m/sとほぼ等しいから、前線付近の下層暖気内の風は前線にほぼ平行である。また高度1.2km以上では直交成分が極めて小さく、線状対流で上昇した境界層内の空気が、大部分前線の後方に移動していることと対応している。
図13はレーダ観測から作成された時間高度断面内の循環である。CFは前線の位置を示す。場が時間的に変化せずに移動すると仮定すると、1時間がおよそ40kmに対応する。太実線は前線帯あるいは安定層の境界で、細実線は前線に相対的な流線を示す。図のスケールで見ると、前線面は地上から高度1km付近までほぼ鉛直で、その後方ではおよそ1/40の割合で傾斜している。前線付近で急激に上昇した空気は、最大上昇流高度より上の寒気側で下降流となっているが、その後方では前線面より少し大きい傾斜で上昇している。傾斜した流れは大局的に見れば暖気内で上昇、前線帯内および寒気内では下降流で、図2bの模式図に類似の循環と言える。なお地上付近で前線から遠ざかる流れになるのは、地表摩擦による減速の影響と説明されている。図からわかるようにこの寒冷前線はアナ型である。この図の他の記号の説明は省略するが、図では断面に垂直な流れ(前線に平行な流れ)が大きいこと(後述、図14)に注意して解釈する必要がある。線状対流の特性と大きな鉛直流の要因を検討する。前線通過1時間前のゾンデ観測によれば、暖気内はほぼ中立成層であった。このことと図12で上昇流が1.2kmより上で急激に減少していることから、線状対流は自由対流*よりも強制対流*の性格が強いと見られる。図13の寒冷前線のすぐ後方の高度2~3kmの下降流は、安定成層中を上昇したことから生ずる負の浮力によるものと考えられる。
図12で述べたように、前線付近の下層では暖気内の風は前線にほぼ平行である。図11の等圧線を参照すると、地表摩擦の影響で前線近傍の地上付近の風は、暖気内では前線にほぼ平行になり、寒気内では前線に向かう成分を強める。つまり地上摩擦により前線付近で水平収束が強められる。これを移動する前線に相対的な流れで考えると、図12、図13に示すように、下層暖気の前線面への大きな流入になる。力学的には摩擦収束は次のように説明される。 |
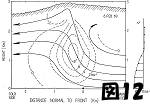
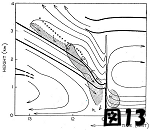
|

*: 重力不安定や対称不安定(後述)など、不安定性によって生ずる対流を自由対流、不安定性が無いときに強制によって生ずる対流を
強制対流と呼び、摩擦収束で強制されるものや、地形による強制で生ずる対流がある。
 |
図14に平行成分の時間高度断面図を示す。前線から数km暖気側の高度1km付近では、24m/sの下層ジェットがあるが、前線の寒気側で10m/sまで急激に弱くなり、10-3s-1を越える大きな低気圧性シアー(正の渦度の鉛直成分、以後’鉛直成分’を省略))が存在している。総観スケールで見ても寒冷前線に沿って大きな正の渦度が存在することは図11の気圧分布からも推定できる。正渦度が大きい所では、大きな摩擦収束と大気境界層上端での大きな上昇流が期待される。大まかな見積もりによると、図12の上昇流の大きさは摩擦収束でほぼ説明できる。寒冷前線前縁の線状対流の上昇流が、地表面摩擦で生ずる循環の収束で説明できることは、線状対流が強制対流であったとの推定を補強する。
図15は降水強度の時間高度断面図である。大気中の降水強度は、レーダー受信強度から、Z-R関係を用いて推定して3階級で表示され、地上降水強度は横軸に示されている(値は縦軸)。太実線は前線帯と安定層の境界を、矢印付き実線は流線を、太点線は降水粒子の軌跡を示す。細い破線は、湿球温位が高さ方向に等しい領域で、前線面より高い高度から発生している小規模な対流の範囲を示す。降水粒子は前線付近の高度3km以下で最も急激に成長し、巾の狭い寒冷前線性降水域を生成している(軌跡②、③)。11時30分付近では下降流により降水強度が弱くなっている。軌跡④、⑤は斜めに上昇する領域で生ずる降水である。⑥は上層で発達する対流雲から生じているが、斜めの上昇流域に比べて降水強度は弱い。上に示した結果から日本付近の寒冷前線性降水域の検討の参考になる点をまとめる。
|
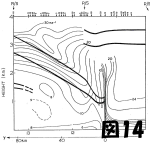
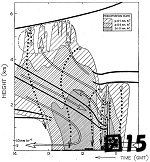
|
|
|
(1)線状対流の生成と寒冷前線
線状対流を引き起こす摩擦収束は、前線付近の境界層上端に大きな正の渦度が存在することにより生ずる。前線付近の大きな渦度の生成は立ち上がり効果よりも水平収束の効果が大きいであろう。図2a,図2bに模式的に示す前線の周りの2次循環は、下層境界付近で水平収束を生じる。すなわち線状対流は、前線形成と一体の現象と見られる。しかしこれは一般論であり、線状対流が発生する場合と発生しない場合の差を検討するのが課題となる。幅の狭い線状対流は正渦度が前線に沿って集中することにより生ずると仮定した場合、それを大きく支配する要素はなんであろうか。数値予報のGPVで検討することが可能であろうか に、 2004年4月27日12時のレーダー画像を示す。南西諸島の東に北東から南西に延びる巾10km程度の細長いエコーがある(立平、2006)。3次元的なセル構造が不明瞭で、細長く延びている。ブラウニングとハロルド(Browning and Harrold(1970)は、このようなエコーを生ずる運動を線状対流(line convection)と呼んだ。
|
(2)線状対流と下層ジェット
この事例の特徴は、前線の暖気側に20m/sを越える強い下層ジェットが存在していたこと、前線付近の高度1.2kmに8m/sの強い上昇流が存在していたである。但し大きな摩擦収束は大きな渦度により生ずるから、絶対値で強い風の存在は必ずしも必要ないとも考えられる。 |
(3)寒冷前線性降水域
この事例の巾の狭い寒冷前線性降水域は、摩擦収束で生ずる線状対流によって生成されている。前線後方に存在する降水域あるいは、図3に見られる巾の広い寒冷前線性降水域は(存在しない場合も含め)巾の狭い降水域とは別に、より広域の寒冷前線あるいは環境場の特徴と関連させて検討すべきであろう。
次回は別の報告を調べ、日本付近の事例を考察する際の問題点を更に検討する。 |