4.寒冷前線性降水域(その2)
前回に引き続き、寒冷前線前縁の線状対流の事例を調べる。
なお以下の本文中で、これまでの解説から引用している図表は、該当部分にリンクを張ってあるので此所から図表を確認して下さい。 |
図16は、図9のロープクラウドに直交する直線AA'に沿う断面内の場を示す。このうち図16(a)には鉛直流(破線,m/s)と温位(実線,K)が、図16(b)には温位(実線,K)、前線に平行な風速(破線,m/s)、特定レベルの風(風向は北が上、風速はノット)が示されている。(シャピロとカイザー(既出)およびボンドとシャピロ(Bond and Shapiro、1991))
この事例では、図の時刻にロープ雲の場所での降水を観測していない。上昇流の最大値は、4m/sでブラウニングとハロルドの事例(図12)より弱いが、巾2km弱の狭い範囲の強い上昇流、進行前縁での上昇、直後の下降は類似している。温位の分布から、下降後のゆるやかな上昇も推定される。水平収束はおおむね高さ800m以下にある。図(b)を見ると、この事例でも前線の前方1kmの高さ1000m付近では前線に平行に20m/sの強い風が吹いている。前線の寒気側では、前線に平行な風速は10m/sまで減じていて、大きな正渦度が摩擦収束を引き起こす可能性を示唆している。
ボンドとフリーグル(Bond and Fleagle、1985)は、ドロップゾンデや飛行機観測デーを用いて、アラスカ湾で発達した低気圧に伴う寒冷前線の総観スケールとメソスケールの運動場と温度場の構造を解析した。
|
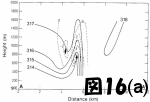
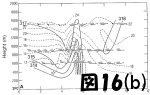 |
図17(a)に、1980年11月16日00UTCの地上天気図、図17(b)に850hPaの上層天気図を示す。図(a)の実線は、地上等圧線(4hPa毎)、破線は1000hPaと700hPaの等層厚線(30m毎)を示す。図(b)の実線は、等高線(30m毎)、破線は等温線(4℃毎)である。前線は既に閉塞しているが、寒冷前線部分が調べられている。地上前線の進行前方およびトラフ軸の下流では非常に強い風が吹いている。 |
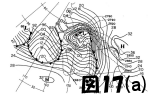
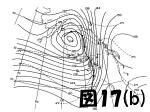
|
以下前線に直交する断面で議論する。(図18参照)
図18の(a)に、航空機観測による地上寒冷前線付近の鉛直流を示す。点線は飛行経路、細実線が鉛直流(m/s)、太実線は307Kの等相当温位線を示し、ここでは前線の目安とされている。横軸は307Kの等値線と地表面との交点からの距離である。これまでに示した例(図12、図16)と比較すると、上昇域の水平スケール(幅5km程度)がやや大きいが、上昇流の最大が大気境界層上端付近にあることは類似している。前線の後面に下降流が見られること、その後方では斜めにゆっくり上昇する流れが存在していることも前の事例と同様である(図省略)。
図18の(b)は、前線に平行な風の分布である。850hPa付近では前線の前方5kmに40m/sの下層ジェットがある。一方、前線付近では28m/s〜20m/sまで風速が減少していて、大きな渦度が存在している。この事例でも図(a)の鉛直流の大きさは、前線の前方5kmまでの平均的な摩擦収束でほぼ説明できる。
論文ではメソスケールの前線形成に対する線状対流の役割が詳しく議論されている。幅の狭い寒冷前線性降水域の考察には、これは重要な点である。しかし、日本付近の事例ではメソ構造を議論するデータが無いので、ここでは省略する。これらの点に興味ある方は、類似な事例についてのサンダース(Sanders、1955)の解析が小倉(2000)や山岸(2007)に紹介されているので参照されたい。
ここではソーヤー・エリアッセン方程式(式(1)、x軸に平行な断面内の循環の式)で、総観規模の2次循環と地表面摩擦の関係を調べる。
|
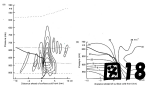
|
◆ソーヤー・エリアッセン方程式◆
(∂θ/∂p)(∂ω/∂x)−(2/γ)(∂m/∂p)(∂u'/∂x)+(1/γ)(∂m/∂x)(∂u'/∂p)=−2(∂U/∂x)(∂θ/∂x)−2(∂V/∂x)(∂θ/∂y)+(1/γ)∂/∂p{(1/ρ)∂τ/∂z}+∂/∂x(dθ/dt) −−−−−−−−−−−− (式1) |
ここでU,Vは、前線に直交および平行な地衡風成分、u'は非地衡風成分、m=V+fxは絶対運動量で、∂m/∂x=f+∂V/∂xは地衡風絶対渦度である。γは温度風の関係式に表れるpの関数、その他は慣例の記号である。
断面内の流線をΨとし、ω=∂Ψ/∂x、u'=−∂Ψ/∂pとおけば、左辺はΨについての2次の偏微分方程式となる。右辺の強制力(地衡風による変形項、摩擦項、非断熱項)を与えてΨについて解けば、対応する2次循環が得られる(図2の模式図参照)。論文ではΨに置き換えずに、観測値から計算した強制項の空間分布や大きさを比較して、各強制項の2次循環生成への寄与を定性的に議論している。 |
|
図19(a)は、左辺の各項を観測データから計算した和(10-10Km-1s-1)で、強制項の分布の基準と考える。図の一点鎖線は、相対渦度の極大値を連ねた線である。700hPa付近に極大値、900hPa付近に極小値が見られる。
図19(b)は、右辺の地衡風の変形だけから計算した強制である。700hPa付近の極大値は、数値は異なるがおおむね図(a)の場合と対応している。しかし地衡風の強制では、900hpa付近の極小値が現れていない。
図19(c)は、地衡風、摩擦、非断熱項から計算したの強制の和である。地表面からの顕熱輸送による非断熱効果は凝結に比較して小さく、結果として無視できる。図19(b)、(c)を対比すると、700hPa付近で強制の大きさが増加していて凝結による非断熱効果である。900hPa付近に中心を持つ強制は、地表面摩擦により生じている。
図19(a)の強制から生ずる2次循環を検討する。循環の分布や強さは強制項のみならず、式(1)の係数にも依存するので、定性的に流れのセンスのみ考える。プラスの強制は反時計回りの循環、マイナスは時計回りの循環を生ずる。700hPa付近の強制は、渦度極大の軸の暖気側で上昇、寒気側で下降のセンスとなる。900hPa付近の極小は、地表摩擦で引き起こされる低圧側への流れが、前線付近の正渦度による摩擦収束で上昇流を生ずる強制を示していると見られる。二つの強制の極大(小)の位置が水平方向にずれていて、下側の上昇成分が上側の上昇成分につながる配置になっている。
図19各図で示した2次循環を先の解説で示した図2(a)と比較する。図2はy軸に平行な断面の循環の模式図である。摩擦と非断熱効果を無視し、温度風の関係、γ∂θ/∂y=∂U/∂p、γ∂θ/∂x=−∂V/∂pを用いて温位の項を書き換え、さらに伸張変形のみとした場合である。式(1)で右辺第1項のみとした場合に相当する。図2では、地衡風強制が強いところ(黒丸の密度が大きいところ)が地表付近まで存在しているが、図19(b)では存在していない。地衡風強制と摩擦をあわせた強制(図19(c))で、模式図に類似して地表から中層まで延びる強制が見られる。
|
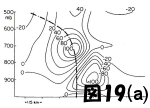
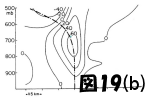
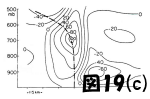
|
これまで紹介した事例は、高緯度(英国、アラスカ湾)で、季節的には2月(ブラウニングとハロルド)、12月(シャピロとカイザー、ボンドとシャピロ)、11月(ボンドとフリーグル)など寒い季節であった。一方でザイターとミュンヒ(Seitter and Muench、1985)は、フロリダ半島を通過した寒冷前線に伴うロープ雲(1983年5月4日)を解析し、ロープ雲は低緯度で多く観測されると述べている。更にロープ雲とそれに付随する、気温,風,気圧擾乱の移動速度が重力流の速さとほぼ等しかったことから、ロープ雲を重力流に伴う現象(アーク雲)として、図20の模式図を提出した。
図では、寒冷前線面に発生した積乱雲からの降雨の蒸発で冷却した冷気流が、重力流として前線より速い速度で移動して、ロープ雲を形成するとされている。但しロープ雲の後方の前線構造の解析は示されていない。日本付近の事例を調べるときに参考にすべき点を追加する。
|
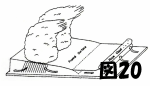
|
|
|
(1)季節と地域
ここで説明した外国の4つの事例では、低緯度のフロリダ半島で暖かい季節に発生した事例だけが、重力流の特性が強調されている。日本付近の事例はフロリダ半島の事例と同じような緯度である。季節や地域により、発生機構に違いがあるだろうか。
|
(2)低気圧のライフサイクル
高緯度の寒い季節に発生した外国の3事例とも、対流圏下層では寒冷前線の後方よりも前方で風速が強く、下層ジェットの存在が指摘されている(例えば図17(a))。日本の事例はこの傾向が明瞭でなく、寒冷前線の後方で風が強い。フロリダ半島の事例も同様である(先に解説の図8参照)。この差は低気圧の発達段階の違いによるのだろうか。
外国の3事例は大陸の西側で、海洋上で発達した最盛期の低気圧を扱っている。一方日本とフロリダ半島の事例は大陸の東側であり、日本の事例は発生初期または発達期である。日本でも低気圧が発達して三陸沖へ移動したときは、低気圧の東側で風速が強くなる事例が多い。この違いが発生機構の差をもたらすであろうか。
(3)寿命
線状対流の継続時間(寿命)はどの程度なのだろうか。線状対流が発生する場合と発生しない場合の差を検討するとき、線状対流が一時的な特性か、長続きする特徴かは興味ある点である。
(4)地表摩擦と渦度分布の空間スケール
図17(a)から推定されるように、地上風は地表摩擦によって前線の前方では前線と平行に、後方では前線に直交する傾向となる。従って総観規模でみても、地表摩擦から前線付近で渦度の鉛直成分が増大する。一方、線状対流の生成機構とされた前線に平行な成分の風速変化(図14、図16(b)、図18(b))は、前線の移動速度にもよるが空間スケールで数km、時間スケールで数分のオーダーである。このスケールの差を念頭に置きつつ、総観スケールの観点で日本の事例を今後検討してみたい。
|
| 2008年7月13日 山岸 米二郎 |

◆参考文献
Bond, N. A. and R. G. Fleagle, 1985: Structure of a cold front over the ocean. Quart. J. R. Met. Soc., 111, 739-759.
Bond,N.A. and M.A. Shapiro,1991: Research aicraft observations of the mesoscale amd microscale structure of a cold front over the Eastern Pacific Ocean. Mon. Wea. Rev., 119, pp 3080-3094.
Seitter,K.L.and H.S. Muench,1985: Observation of a cold front with rope cloud. Mon. Wea. Rev., 113,. pp840-848.
Sanders、F., 1955: An investigation of the structure and dynamics of an intense surface frontal zone. J.Meteor., 12, pp542−552.
小倉義光、2000:総観気象学入門。東京大学出版会。 山岸米二郎、2007:気象予報のための前線の知識。オーム社 |