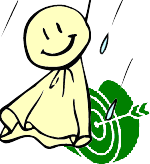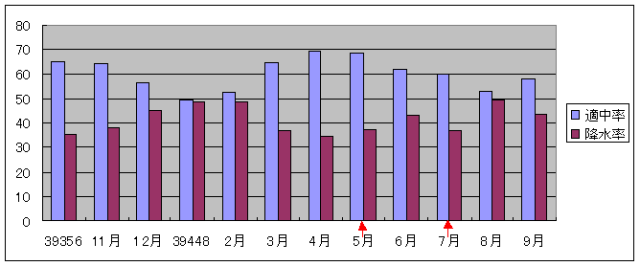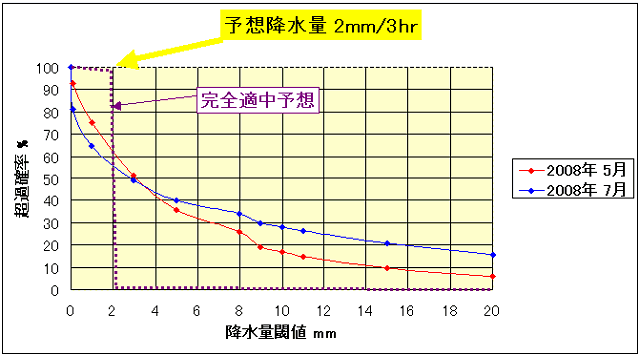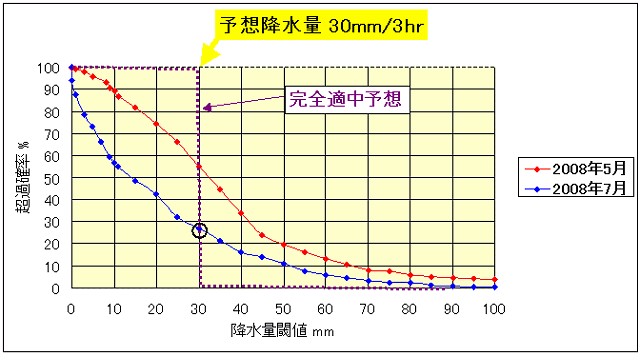| 気象技術の教室 4 | |||||||||||
「教室2」では、MSM降水量予測の精度を月毎の「分割表」と「超過確率分布」の形で掲載しているが、1年分のデータがまとまったので、精度の季節変化など若干の考察を試みた。 ◆ 適中率と降水率の月毎の変化 図1は、教室2掲載の分割表から求めた「適中率」と「降水率」の月毎の変化である。予報の精度検証には、「明日の降水の有無予報」のように「Yes」「No」の2x2の分割表が一般に用いられているが、量的予報の場合は「教室2」のように、4x4とか5x5の分割表を使うほうがより詳細な精度情報を得ることができる。一般に、閾値の数を増やすほど「適中率」が低下することは容易に分る。
図1によれば、春と秋に適中率が高く、夏と冬に適中率が低下する傾向がある。関東地方など太平洋側では、冬は降水率が低く適中率が高いというのが実感であるが、図1は日本海側の冬型降水による高降水率の影響を強く受けているものと考えられる。 図1は「適中率」と「降水率」の間には高い逆相関のあることを示している。この性質は、例えば「明日の降水の有無予報」でも認められている。2008年夏の適中率の低下は、かなりの部分が降水率の高さで説明される。しかし詳細に見ると、2008年の5月と7月のように、降水率に殆ど差がないのに適中率が10% 近く違っているケースもある。( 図1の矢印 ) ◆ MSMが2mm/3hrと予想したときの超過確率 教室2の右側に掲載している「超過確率」では、5月と7月でどのような差が認められるか比べてみよう。 図2は、MSMが2mm/3hrと予想したときの超過確率である。もし予想が正確でいつも2mm/3hrの降水があったとしたら、点線のような超過確率になることは容易に分る。 超過確率曲線がこの完全適中超過確率に近いほど、精度が高いといえる。
このような観点で図2を見ると、降水量閾値2mmより大きいところで5月の超過確率曲線(赤線)の方が全体として下方にあり、より点線に近く、7月より予想精度が高いといえる。降水量閾値2mmより小さいところでは、5月 (赤線)の方が上方にあって完全適中予想線に近いので、やはりより精度が高いといえる。 ◆ MSMが30mm/3hrと予想したときの超過確率 図3はMSMが30mm/3hrと予想したときの超過確率である。 7月(青線)は降水量閾値30mmの線と確率30%付近で交わっている(黒丸)。もし予想にバイアスがなければ、閾値を超える確率は50%の筈だから、7月の降水量予想は過小といえる。一方、5月 (赤線)は降水量閾値30mmの線と確率50%付近で交わっており、バイアスが小さいといえる。 精度の観点からすると、図3は降水量閾値が30mm/3hrより小さい領域では赤線の精度が高く、30mm/3hrより大きい領域では青線の精度が高いことを示し、全体としての精度は明確ではない。結局、5月の適中率が7月より高いのは、弱い雨がよく適中していたことが主原因と考えられる。
|